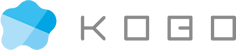「夏涼しく冬暖かい家」を求めて、RC外断熱へ建て替え。

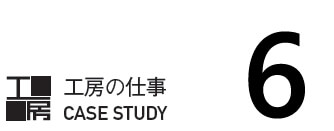
2階LDKのRCならではの広い空間。
ダイニングの白い棚の奥は1階からの階段で、吹き抜けから光が注ぎ込む。
ご主人が腰を下ろす。螺旋階段は、屋上へ。
建て替える前の家は、有名建築家の手になるL字型木造2階建てで、外壁6面のうち3面が総ガラス張りという家だった。
施主Tさんいわく「とてもかっこいい家だったのですが、とにかく夏は暑いし、冬は寒かった」。そこで、ガラス面を壊して断熱材の入った壁にリフォームしようと計画していたところに、3・11の大震災が来た。木造の外壁にヒビが入って、そこから雨水が浸入したりして、やむなく計画の見直しを迫られた。
その木造を建て替えることを視野に、Tさんはハウスメーカーや建築会社の展示場を徹底的に見てまわり勉強した。そんなとき、たまたま知人宅で工房のRC外断熱を知り、工房も検討のなかに入れた。そして、築13年の木造をRCに建て替えることにした。3社のコンペとなり、最終的に工房に決まった。
「別の1社の攻勢がすごくて、模型などもどんどんつくってきて、これがまたかっこいいわけです。でも、長い時間ああでもないこうでもないと話しているなかで、結局決め手になったのは、工房の設計士の存在でした。やっぱりプロの意見は聞くもんだなあ、と思わせられる場面がいくつもあったわけです」
施主Tさんいわく「とてもかっこいい家だったのですが、とにかく夏は暑いし、冬は寒かった」。そこで、ガラス面を壊して断熱材の入った壁にリフォームしようと計画していたところに、3・11の大震災が来た。木造の外壁にヒビが入って、そこから雨水が浸入したりして、やむなく計画の見直しを迫られた。
その木造を建て替えることを視野に、Tさんはハウスメーカーや建築会社の展示場を徹底的に見てまわり勉強した。そんなとき、たまたま知人宅で工房のRC外断熱を知り、工房も検討のなかに入れた。そして、築13年の木造をRCに建て替えることにした。3社のコンペとなり、最終的に工房に決まった。
「別の1社の攻勢がすごくて、模型などもどんどんつくってきて、これがまたかっこいいわけです。でも、長い時間ああでもないこうでもないと話しているなかで、結局決め手になったのは、工房の設計士の存在でした。やっぱりプロの意見は聞くもんだなあ、と思わせられる場面がいくつもあったわけです」
 黒松が立つ街の警官に溶け込んだ外観。まずは敷地内にあっても、私の所有物で、管理は地主が行う、と言う風致地区ではのルールがある。
黒松が立つ街の警官に溶け込んだ外観。まずは敷地内にあっても、私の所有物で、管理は地主が行う、と言う風致地区ではのルールがある。 1階から2階への階段。吹き抜け口が差し込み、1階まで明るい。
1階から2階への階段。吹き抜け口が差し込み、1階まで明るい。砂地に湧く地下水を、確実な工法でシャットアウト。
周辺には市川市の木にもなっている黒松の木が多く、雰囲気のある町並みが続く。そんなわけで、この周辺は風致地区に指定されていて、建ぺい率40%、容積率80%と非常に厳しい条件がある。ご夫婦に高3と中3の息子さんという家族構成。
2人の息子さんの個室も含めて要望に沿った間取りを実現するために、地下室を設けることにした。
しかし、そこで問題になったのが地下水だった。貝塚遺跡の多いこの地区はもともと海岸地帯であり、どこを掘ってもすぐに崩れる砂質土で、地下2mで水も出てくる。だから周辺には地下室の例はあまりない。それでも、技術的にできないわけではない。
工房は建設地の地下水を抜き続けて、建設地の水位を周辺よりも下げるウェルポイント工法を用い、また、タケイ防水工法でRC躯体自体を防水し、さらに地下は2重壁とした。
 キッチンにてT夫妻。「普段はここにはほとんど入ったことがないけど」とご主人。白い壁にCUCINAのシステムキッチンが映える。
キッチンにてT夫妻。「普段はここにはほとんど入ったことがないけど」とご主人。白い壁にCUCINAのシステムキッチンが映える。
 リビングの床は無垢のクルミ材、壁面は大理石の飾り壁、棚はCUCINAのシステムキッチンに合わせた注文家具と、随所にTさんのこだわりが見える。
リビングの床は無垢のクルミ材、壁面は大理石の飾り壁、棚はCUCINAのシステムキッチンに合わせた注文家具と、随所にTさんのこだわりが見える。
 エントランスと玄関。右下が地下のドライエリアとなる。
エントランスと玄関。右下が地下のドライエリアとなる。
 地下のドライエリアと地下室。ここが地下であることを忘れる明るさ。
地下のドライエリアと地下室。ここが地下であることを忘れる明るさ。
2人の息子さんの個室も含めて要望に沿った間取りを実現するために、地下室を設けることにした。
しかし、そこで問題になったのが地下水だった。貝塚遺跡の多いこの地区はもともと海岸地帯であり、どこを掘ってもすぐに崩れる砂質土で、地下2mで水も出てくる。だから周辺には地下室の例はあまりない。それでも、技術的にできないわけではない。
工房は建設地の地下水を抜き続けて、建設地の水位を周辺よりも下げるウェルポイント工法を用い、また、タケイ防水工法でRC躯体自体を防水し、さらに地下は2重壁とした。
 キッチンにてT夫妻。「普段はここにはほとんど入ったことがないけど」とご主人。白い壁にCUCINAのシステムキッチンが映える。
キッチンにてT夫妻。「普段はここにはほとんど入ったことがないけど」とご主人。白い壁にCUCINAのシステムキッチンが映える。 リビングの床は無垢のクルミ材、壁面は大理石の飾り壁、棚はCUCINAのシステムキッチンに合わせた注文家具と、随所にTさんのこだわりが見える。
リビングの床は無垢のクルミ材、壁面は大理石の飾り壁、棚はCUCINAのシステムキッチンに合わせた注文家具と、随所にTさんのこだわりが見える。 エントランスと玄関。右下が地下のドライエリアとなる。
エントランスと玄関。右下が地下のドライエリアとなる。 地下のドライエリアと地下室。ここが地下であることを忘れる明るさ。
地下のドライエリアと地下室。ここが地下であることを忘れる明るさ。
所在地:千葉県市川市
竣工:2013年9月
用途・規模・構造:専用住宅・鉄筋コンクリート造・地下1階 地上2階 PH1階建
断熱:外断熱/EPS湿式張り+レオトップ打込み
敷地面積、建築面積:敷地面積 144.76㎡、建築面積 84.97㎡
延床面積、各階面積:延床面積 207.37㎡
設計:株式会社工房 一級建築士事務所